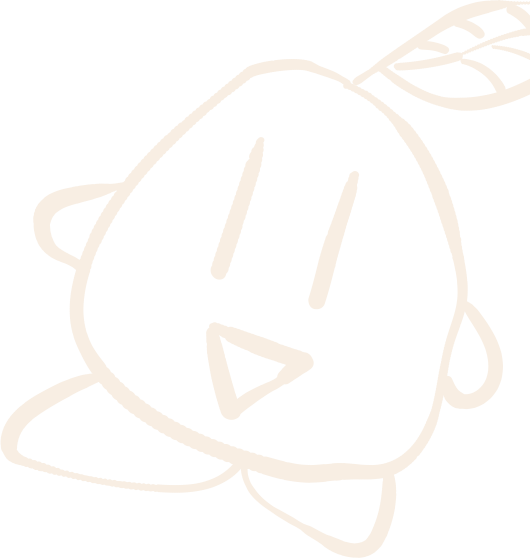月末、年中さんと年長さんがホールで“うたの会”を行っていました。
月末、年中さんと年長さんがホールで“うたの会”を行っていました。どのクラスもまぁ、ステージ前に立つと、前を向いて歌っています。『お客さん』を意識できているのかな。『前で歌う』という行為に、ほんのりフォーマルな雰囲気を感じ取っているのかな。
普段はワイワイ元気な子どもたちですが、園生活の中で色んな場面を経験して、感じ取って、育ってくれているんですね。
 ついつい撮っちゃう水遊び。タイミング的に年少さんが多くなってしまいます。他の学年も狙っていくぞー。
ついつい撮っちゃう水遊び。タイミング的に年少さんが多くなってしまいます。他の学年も狙っていくぞー。 これは、環境机に置いてあったピーマンを抱えて事務所に遊びに来た子と一緒に作った、ピーマンの赤ちゃん。
これは、環境机に置いてあったピーマンを抱えて事務所に遊びに来た子と一緒に作った、ピーマンの赤ちゃん。園の毎日。残しておきたい場面も、瞬間も、たくさん。
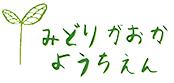

 年長さんに向けて、2回目の「からだ・いのちのはなし」を助産師はぐ先生にしていただきました。
年長さんに向けて、2回目の「からだ・いのちのはなし」を助産師はぐ先生にしていただきました。 そんな年長さん、午後の時間になにやらコンコンと音がするなーと思って覗きに行くと、“たたき染め”をしている真っ最中。
そんな年長さん、午後の時間になにやらコンコンと音がするなーと思って覗きに行くと、“たたき染め”をしている真っ最中。 私も他の園さんで教えてもらうまでは知らなかったんですが、ほら、葉っぱやお花を布の上でたたくだけでこんなにしっかり色がつく。おもしろいね。
私も他の園さんで教えてもらうまでは知らなかったんですが、ほら、葉っぱやお花を布の上でたたくだけでこんなにしっかり色がつく。おもしろいね。 年少さんが泥んこ遊びをしていると、当たり前のように外遊びをしていた2歳児さんたちがやってきて、なんだかワイワイやっています。
年少さんが泥んこ遊びをしていると、当たり前のように外遊びをしていた2歳児さんたちがやってきて、なんだかワイワイやっています。 水遊びの日は保護者の方が『水遊び見守り隊』としてお手伝いに来て下さっています。子どもたちはすぐに覚え、「〇〇くんのおとうさーん!」と元気に呼び掛けていました。
水遊びの日は保護者の方が『水遊び見守り隊』としてお手伝いに来て下さっています。子どもたちはすぐに覚え、「〇〇くんのおとうさーん!」と元気に呼び掛けていました。  みんなで思いおもいに遊びこむ、保育満喫デイ。子どもたちはステキな保育デイと言っています。私が途中で名称を満喫デイにしようとしたのですが、なんだか先生たちにも子どもたちにもステキな保育デイですっかり定着しています。
みんなで思いおもいに遊びこむ、保育満喫デイ。子どもたちはステキな保育デイと言っています。私が途中で名称を満喫デイにしようとしたのですが、なんだか先生たちにも子どもたちにもステキな保育デイですっかり定着しています。 新入児のM君、園庭に立ってじっと二階ていたので、「どうしたの?」と聞くと無言で二階廊下を指さしました。
新入児のM君、園庭に立ってじっと二階ていたので、「どうしたの?」と聞くと無言で二階廊下を指さしました。 上園庭で遊んでいた水が、流れながれて川みたい。バイカーたちがそれに気づきました。
上園庭で遊んでいた水が、流れながれて川みたい。バイカーたちがそれに気づきました。 6月ということで、♪明日天気になあれ のわらべうた遊びもしていました。宙を舞っているのはスリッパです。
6月ということで、♪明日天気になあれ のわらべうた遊びもしていました。宙を舞っているのはスリッパです。 R組ログハウスの縁側で作っているのはてるてる坊主。誰かがクラゲって言っていましたが、なるほど透明だからかな。かわいいね。
R組ログハウスの縁側で作っているのはてるてる坊主。誰かがクラゲって言っていましたが、なるほど透明だからかな。かわいいね。 その隣では、トイレットペーパーの芯をスタンプにして・・・
その隣では、トイレットペーパーの芯をスタンプにして・・・ 最終的にはこんなふうに模造紙いっぱいに雫模様。芯をちょっとつぶすと雫のかたちになるんだね。子どもたちはきっと偶然見つけたのでしょうね。
最終的にはこんなふうに模造紙いっぱいに雫模様。芯をちょっとつぶすと雫のかたちになるんだね。子どもたちはきっと偶然見つけたのでしょうね。 紙にマーカーで模様を描いて、霧吹きでにじませれば不思議な模様になる。軒先でちょっと乾かしたいけど、年少さんでは難しい。
紙にマーカーで模様を描いて、霧吹きでにじませれば不思議な模様になる。軒先でちょっと乾かしたいけど、年少さんでは難しい。 最近、泥んこ遊びは単に『砂に水を混ぜただけ』のものではなくなってきました。
最近、泥んこ遊びは単に『砂に水を混ぜただけ』のものではなくなってきました。 水遊びとはいえ、水にばっしゃーん!キャー!というだけが水遊びではありません。水と色んな関わり方をして、水の性質を知り、夢中になって遊ぶここで素材のことを深く知れるのです。
水遊びとはいえ、水にばっしゃーん!キャー!というだけが水遊びではありません。水と色んな関わり方をして、水の性質を知り、夢中になって遊ぶここで素材のことを深く知れるのです。 泥遊びの傍に、大きな模造紙・・・?
泥遊びの傍に、大きな模造紙・・・? 誰かが掘った砂場の穴に、誰かが水を入れ、誰かが浸かり、誰かが“ぼくもやりたい”とせがむ。
誰かが掘った砂場の穴に、誰かが水を入れ、誰かが浸かり、誰かが“ぼくもやりたい”とせがむ。 水遊び開始とともに梅雨入りしたのでかなか外遊びもままならないこのごろですが、今日は曇り空のなか泥遊びやシャボン玉、色水あそびなどができました。
水遊び開始とともに梅雨入りしたのでかなか外遊びもままならないこのごろですが、今日は曇り空のなか泥遊びやシャボン玉、色水あそびなどができました。 先日、研究会への参加で北海道まで自腹で出かけた職員が、帰ってくるなり「うちの園はもっと子どもへのわかりやすさがいると思うんです!」と速攻で作ってくれた『駐車場』看板。とりあえずでもたちまちでもいい、まずは動いてみることが大切ですよね。
先日、研究会への参加で北海道まで自腹で出かけた職員が、帰ってくるなり「うちの園はもっと子どもへのわかりやすさがいると思うんです!」と速攻で作ってくれた『駐車場』看板。とりあえずでもたちまちでもいい、まずは動いてみることが大切ですよね。 園庭で収穫されたムラサキジャガイモ。
園庭で収穫されたムラサキジャガイモ。 0~2歳児さんのふれあい参観日は『みんなで楽しく ぎゅっぎゅ』と名付けられました。その名の通り、みんながそれぞれ居場所や楽しみを見付けられるように、と先生たちのアイディアや工夫を盛り合わせた内容。
0~2歳児さんのふれあい参観日は『みんなで楽しく ぎゅっぎゅ』と名付けられました。その名の通り、みんながそれぞれ居場所や楽しみを見付けられるように、と先生たちのアイディアや工夫を盛り合わせた内容。 最初はクラスごとに分かれて、子どもたちが普段楽しんでいるわらべうた遊びをみんなでやってみました。
最初はクラスごとに分かれて、子どもたちが普段楽しんでいるわらべうた遊びをみんなでやってみました。 その後は先生たちが開いた“お店”に自由に遊びにいける時間です!粉から作る小麦粉粘土、梅雨にちなんだ水色の絵の具でお絵描き、自分で作るセンサリーボトル、構造遊び、新聞紙遊び、絵本コーナー。
その後は先生たちが開いた“お店”に自由に遊びにいける時間です!粉から作る小麦粉粘土、梅雨にちなんだ水色の絵の具でお絵描き、自分で作るセンサリーボトル、構造遊び、新聞紙遊び、絵本コーナー。 好きなことは何度でも。絵の具がハマったKちゃんは2枚も3枚も絵の具遊びを楽しんでいました。
好きなことは何度でも。絵の具がハマったKちゃんは2枚も3枚も絵の具遊びを楽しんでいました。 園庭が大きく変わってからはじめてのうんどう会。こんな園庭でどうやってやるんだろう?と思われていた方もおられるかもしれませんが、スタート前に園庭を子どもたちが元気に走り回っており、まさに『こんな感じのうんどう会です』を表しているようでした。
園庭が大きく変わってからはじめてのうんどう会。こんな園庭でどうやってやるんだろう?と思われていた方もおられるかもしれませんが、スタート前に園庭を子どもたちが元気に走り回っており、まさに『こんな感じのうんどう会です』を表しているようでした。 漱石と鴎外の間を縫って広がったり、遊んだり。こうして親子約40組が体操してみると、園庭はまだまだ広いなぁ!という感想。こんなに広けりゃなんでもできますね。
漱石と鴎外の間を縫って広がったり、遊んだり。こうして親子約40組が体操してみると、園庭はまだまだ広いなぁ!という感想。こんなに広けりゃなんでもできますね。 普段、なかなか子どもたちとじっくり関わる時間も少なくなっている現代社会。こうして園の行事を通してふれあいの時間を作ることも大切だと思っています。
普段、なかなか子どもたちとじっくり関わる時間も少なくなっている現代社会。こうして園の行事を通してふれあいの時間を作ることも大切だと思っています。 園庭に鎮座する漱石と鴎外も、年少さんのために役立って頂きました。トンネルくぐりになってもらったり、
園庭に鎮座する漱石と鴎外も、年少さんのために役立って頂きました。トンネルくぐりになってもらったり、 “マト”になってもらったり。
“マト”になってもらったり。 正直、『いつ降りだすだろう?』と心配な空模様でしたが、薄曇りの中で子どもも大人も暑さを気にせず身体を動かせました。
正直、『いつ降りだすだろう?』と心配な空模様でしたが、薄曇りの中で子どもも大人も暑さを気にせず身体を動かせました。 最後の親子ダンスは動画配信していたので「お家でいっぱい練習してきたからね」という保護者の声も聞こえて、当日だけじゃなくうんどう会を楽しみにしてくれていたんだなと感じて嬉しくなりました。
最後の親子ダンスは動画配信していたので「お家でいっぱい練習してきたからね」という保護者の声も聞こえて、当日だけじゃなくうんどう会を楽しみにしてくれていたんだなと感じて嬉しくなりました。 2年前に、卒園記念ワークショップをして共に作った事務所横のベンチ。子どもたちのちょっとした憩いの場になっています。絵本や図鑑を置いたら、さらに居心地の良さアップ。
2年前に、卒園記念ワークショップをして共に作った事務所横のベンチ。子どもたちのちょっとした憩いの場になっています。絵本や図鑑を置いたら、さらに居心地の良さアップ。 オジギソウって、こんなにちっちゃくてもちゃんとオジギするんですね。知らなかった。
オジギソウって、こんなにちっちゃくてもちゃんとオジギするんですね。知らなかった。 園庭の一画で年少さんの親子ダンスをしていたら、わいわい集まってきてノリノリで踊ってきたのが年長さん。
園庭の一画で年少さんの親子ダンスをしていたら、わいわい集まってきてノリノリで踊ってきたのが年長さん。 明日に向けての準備が着々を進められています。「せっかくだから」と、お部屋に飾っていた年少さんたちのこいのぼりも出してみた。
明日に向けての準備が着々を進められています。「せっかくだから」と、お部屋に飾っていた年少さんたちのこいのぼりも出してみた。 さていよいよ今週が年少親子ふれあい運動会の“みどりんパーク”。大人の動きの確認もかねて、実際にマイクをつけたり音楽を流してみたりして、“こんな感じ”というのをやってみました。
さていよいよ今週が年少親子ふれあい運動会の“みどりんパーク”。大人の動きの確認もかねて、実際にマイクをつけたり音楽を流してみたりして、“こんな感じ”というのをやってみました。 競技や、テントへの出入りもやってみる。
隊列を組んで入場・退場はありませんが、子どもたちはなかなかどうして競技が始まればテントから出て来て、終われば帰って行きます。
競技や、テントへの出入りもやってみる。
隊列を組んで入場・退場はありませんが、子どもたちはなかなかどうして競技が始まればテントから出て来て、終われば帰って行きます。 練習練習!でなくても、じっくり時間をかけて園庭や遊びや園の人たちに慣れてきたからなのかな。
練習練習!でなくても、じっくり時間をかけて園庭や遊びや園の人たちに慣れてきたからなのかな。 同時刻には年長さんが毎年恒例の梅収穫にでかけていたので、私もあわてて同行。昨年度は梅が不作だったので、ちょっと心配だったのです。
同時刻には年長さんが毎年恒例の梅収穫にでかけていたので、私もあわてて同行。昨年度は梅が不作だったので、ちょっと心配だったのです。 去年は5キロちょっとだったような記憶ですが、今年はカゴ2つにどっさり。計15キロ。
保護者の方にもお手伝いいただいて、収穫からヘタとりまで一緒に作業していただきました。
去年は5キロちょっとだったような記憶ですが、今年はカゴ2つにどっさり。計15キロ。
保護者の方にもお手伝いいただいて、収穫からヘタとりまで一緒に作業していただきました。