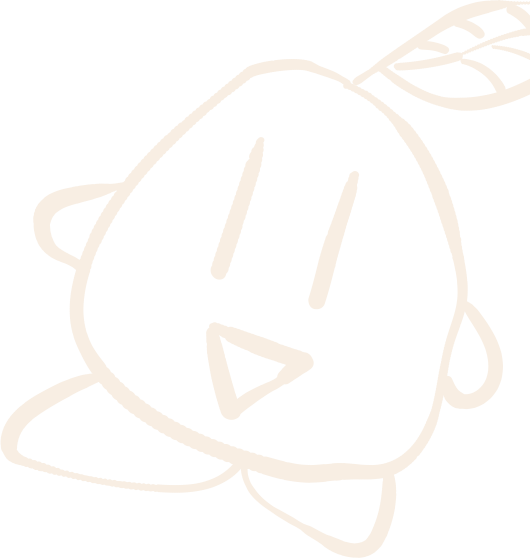今年度、我が町黒瀬町が幼保小連携のモデル地区となり、一番進学児の多い小学校を中心に先生同士の交流、授業参観、公開保育、子ども同士の交流を様々に試みています。
今年度、我が町黒瀬町が幼保小連携のモデル地区となり、一番進学児の多い小学校を中心に先生同士の交流、授業参観、公開保育、子ども同士の交流を様々に試みています。この日は交流の窓口になってくれている専科(図工)の先生が本園に『学校ごっこ』をしに来てくれました。「しょうがっこうといえば、さんすうのじゅぎょうをしてもらいたい!」というS組さんと、「ずこうのせんせいなんじゃろ?じゃあずこうおしえて!」というT組さん。そんな子どもたちの要望を快く受け入れて下さり、本物の小学校教諭による本物の学校ごっこ。こんなの本園初!
ごっことはいえ、小学校のY先生に「これは何だと思う?」「じゃあ手をあげて言ってね」と、本当の授業のような時間を過ごせました。
 各クラスで授業ごっこをしたあとは、年長さんみんなとY先生で一緒に遊びました。最後に、卒園児も多い今の1年生から『昔遊び』の招待状も頂き、今月末にある小学校訪問に向けて子どもたちも大喜び。
各クラスで授業ごっこをしたあとは、年長さんみんなとY先生で一緒に遊びました。最後に、卒園児も多い今の1年生から『昔遊び』の招待状も頂き、今月末にある小学校訪問に向けて子どもたちも大喜び。見覚えのある名前の書かれた招待状。あぁみんな元気に小学生してるんだなぁ。
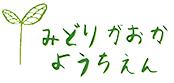

 大寒波の影響で前日の夕方から雪。当日も10時までマイナス気温の予報で、路面凍結の恐れもあり急遽3時間遅れでの開催とさせていただきました。
保護者のみなさま、そして子どもたちにはご心配をおかけしました。
大寒波の影響で前日の夕方から雪。当日も10時までマイナス気温の予報で、路面凍結の恐れもあり急遽3時間遅れでの開催とさせていただきました。
保護者のみなさま、そして子どもたちにはご心配をおかけしました。 各クラスが始まる前、担任から一言ご挨拶をさせて頂きました。今日までの子どもたちの取組み、劇づくりの様子、そして今日のこと。
各クラスが始まる前、担任から一言ご挨拶をさせて頂きました。今日までの子どもたちの取組み、劇づくりの様子、そして今日のこと。 お家の人がそばに見えて、いつもと違う雰囲気に少し気後れした子もいましたし、パワーをもらって持っている力を存分に発揮できた子もいました。
お家の人がそばに見えて、いつもと違う雰囲気に少し気後れした子もいましたし、パワーをもらって持っている力を存分に発揮できた子もいました。 なかなか冬の発表会についてここで取り上げられていませんでした。
なかなか冬の発表会についてここで取り上げられていませんでした。 ・
・ 大きな寒波、冬の園庭。
大きな寒波、冬の園庭。 日本の伝統行事はなかなか大きな変化があるものではありませんが、保育の移り変わりや子どもたちの様子によっては変化して然るべき。
日本の伝統行事はなかなか大きな変化があるものではありませんが、保育の移り変わりや子どもたちの様子によっては変化して然るべき。 「おにがそとにでた!」と子どもたちの誰かが叫ぶと、外で遊んでいた子も立ち竦んだり、隠れたり。
「おにがそとにでた!」と子どもたちの誰かが叫ぶと、外で遊んでいた子も立ち竦んだり、隠れたり。 新聞紙で作った豆を投げ、弱ったところに取ってきたヒイラギや子どもたち自作の“イワシ”を燃やして、扇げ扇げ~~!!
新聞紙で作った豆を投げ、弱ったところに取ってきたヒイラギや子どもたち自作の“イワシ”を燃やして、扇げ扇げ~~!! ヨロヨロと、でも行儀よく門から出て行ってくれた鬼さんに敬意を表して子どもたちも最後までお見送り。
ヨロヨロと、でも行儀よく門から出て行ってくれた鬼さんに敬意を表して子どもたちも最後までお見送り。 紙芝居屋さんの日?
紙芝居屋さんの日? メインのとんど焼き!
メインのとんど焼き! 園のとんどは小さいですが、子どもにとっては大きな炎。それぞれ自分が安心できる距離感で見つめている姿が印象的でした。
園のとんどは小さいですが、子どもにとっては大きな炎。それぞれ自分が安心できる距離感で見つめている姿が印象的でした。