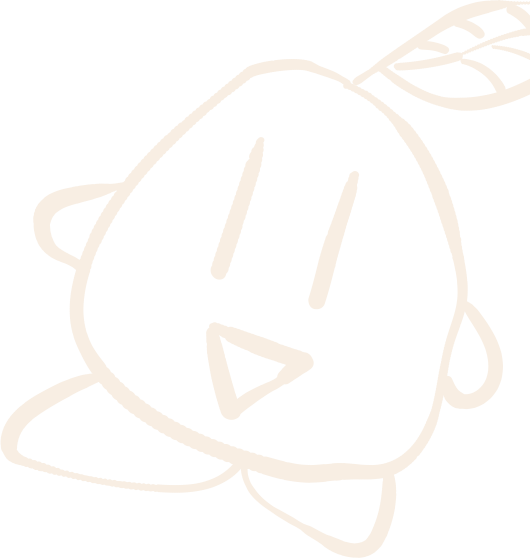保育納めの今日、ちょっとお楽しみを。ということでこの冬初めての焚火をしました。バス運転のH先生が作ってくれたヘキサゴン(6角形)ベンチも使ってみたくて。
保育納めの今日、ちょっとお楽しみを。ということでこの冬初めての焚火をしました。バス運転のH先生が作ってくれたヘキサゴン(6角形)ベンチも使ってみたくて。コンクリートブロックを組んでいると、もう子どもたちはそれだけで集まってきています。
「なにするの?」
「なんでたきびするの?」
「なんか やくの?」
「おもち?」
おもちはまた年が明けてからね。焚火もたくさんやろうね。明日からお休みだけど、元気ですごして、また園で一緒に遊ぼうね。
良いお年を。
2024/12/31
 保育納めの今日、ちょっとお楽しみを。ということでこの冬初めての焚火をしました。バス運転のH先生が作ってくれたヘキサゴン(6角形)ベンチも使ってみたくて。
保育納めの今日、ちょっとお楽しみを。ということでこの冬初めての焚火をしました。バス運転のH先生が作ってくれたヘキサゴン(6角形)ベンチも使ってみたくて。2024/12/27
 1号さんも小学校も冬休みに入り、そんなタイミングで幼稚園・保育園・こども園・小学校の公開保育を行いました。市からの依頼で昨年度に続いて2回目で、昨年は小学校の先生が2名でしたが今年は10倍以上の来場者!
1号さんも小学校も冬休みに入り、そんなタイミングで幼稚園・保育園・こども園・小学校の公開保育を行いました。市からの依頼で昨年度に続いて2回目で、昨年は小学校の先生が2名でしたが今年は10倍以上の来場者!2024/12/24
 みどりがおかの「み」をひっぱって、本園では「3」の付く日にプチ環境整備をしています。同じように環境整備をされている保育園さんのマネっこです。よいものはどんどんマネしていくんです。そんな園です。
みどりがおかの「み」をひっぱって、本園では「3」の付く日にプチ環境整備をしています。同じように環境整備をされている保育園さんのマネっこです。よいものはどんどんマネしていくんです。そんな園です。2024/12/24
 こんな年末の学期末に、という声も聞こえてくるような来ないようなですが、新しい試みを始めてみた年長さん。
こんな年末の学期末に、という声も聞こえてくるような来ないようなですが、新しい試みを始めてみた年長さん。 今日はホールで2学期が終わる式を3・4・5歳児さん みんなで行いました。
今日はホールで2学期が終わる式を3・4・5歳児さん みんなで行いました。 昨日はお誕生日会のお楽しみ会。ハンバーグはトナカイさん。
昨日はお誕生日会のお楽しみ会。ハンバーグはトナカイさん。2024/12/19
 年末に向けてのおもちつき。上園庭で準備が始まると、子どもたちはわくわく集まってきます。
年末に向けてのおもちつき。上園庭で準備が始まると、子どもたちはわくわく集まってきます。 支援センターさんも園児も一緒になっておもいつきを応援します。
支援センターさんも園児も一緒になっておもいつきを応援します。 おもちを丸めるためにスタンバイしている先生たちも、わいわい雑談しながらつきあがるのを待っています。
おもちを丸めるためにスタンバイしている先生たちも、わいわい雑談しながらつきあがるのを待っています。2024/12/19
 朝、霜が降りるようになりましたね。ということは、朝イチで園庭に出た子たちがカップとスコップを持って霜を集めるお仕事を始める時期でもあります。
朝、霜が降りるようになりましたね。ということは、朝イチで園庭に出た子たちがカップとスコップを持って霜を集めるお仕事を始める時期でもあります。 砂場の枠にも霜を発見!霜集め職人が増えました。低い場所だから取りやすいね。
砂場の枠にも霜を発見!霜集め職人が増えました。低い場所だから取りやすいね。 おや、そんなところにも?
おや、そんなところにも?2024/12/19
 休日の手慰みに毛糸で作ったオーナメント。子どもたちでもできるんじゃないかな、と思って持ってきました。カンタンにやり方を教えて、あとはそんなに気にせず任せてみたら、こんなあったかそうなのが出来上がっていました。
休日の手慰みに毛糸で作ったオーナメント。子どもたちでもできるんじゃないかな、と思って持ってきました。カンタンにやり方を教えて、あとはそんなに気にせず任せてみたら、こんなあったかそうなのが出来上がっていました。 例年、2月に交通安全指導がてら歩いて行っていた小学校訪問ですが、今年は子どもたちの進学への期待感がゆるやかに増していってほしいな、と思っていつもより早めの時期にお伺いしました。
例年、2月に交通安全指導がてら歩いて行っていた小学校訪問ですが、今年は子どもたちの進学への期待感がゆるやかに増していってほしいな、と思っていつもより早めの時期にお伺いしました。 小学校は何でもスケールが大きい。
小学校は何でもスケールが大きい。 図書室で学校の先生に質問する時間も作ってもらえました。
図書室で学校の先生に質問する時間も作ってもらえました。2024/12/19
 園の様子ではないのですが・・・今日は出張で兵庫県まで。
園の様子ではないのですが・・・今日は出張で兵庫県まで。 訪問した園の“環境リーダー”さんに、藍のたたき染め を教えてもらいました。
訪問した園の“環境リーダー”さんに、藍のたたき染め を教えてもらいました。 そういえば、ちょっと前にワークショップで作った新しい遊具の名前が決まりました。
そういえば、ちょっと前にワークショップで作った新しい遊具の名前が決まりました。2024/12/19
 午前中出入り自由の自由参観、それぞれの場所、それぞれ好きなことで遊ぶいつもの子どもたちの姿を見て頂きました。
午前中出入り自由の自由参観、それぞれの場所、それぞれ好きなことで遊ぶいつもの子どもたちの姿を見て頂きました。
 体調不良でお休みが多いクラスもありましたが、中でも外でも自分の好きな遊びを見付けて遊び込む、そんな3歳児さんの姿を見て頂けたかなと思います。
体調不良でお休みが多いクラスもありましたが、中でも外でも自分の好きな遊びを見付けて遊び込む、そんな3歳児さんの姿を見て頂けたかなと思います。2024/12/11
 先日抜いたかぶを、漬物にしました。キッチンの栄養士さんが来てくれて、3色栄養のお話しを聞いてからのクッキング?です。
先日抜いたかぶを、漬物にしました。キッチンの栄養士さんが来てくれて、3色栄養のお話しを聞いてからのクッキング?です。 お話しを聞いた後はかぶを漬けこみます。とはいってもみんなでモミモミする・・・というクッキング内容ですが、それでも漬物ってこういう作り方もあるんだね、と貴重な体験。
お話しを聞いた後はかぶを漬けこみます。とはいってもみんなでモミモミする・・・というクッキング内容ですが、それでも漬物ってこういう作り方もあるんだね、と貴重な体験。